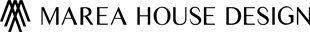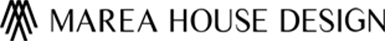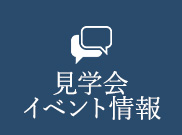栃木県について考えてみたいと思います。 栃木県は、関東地方北部に位置しますが、実際に東は茨城県になり、西には群馬県、南側には茨城県、埼玉県、群馬県の三県。そして北には、福島県と接した内陸県になり、首都である東京からは、北 … “栃木県について考える” の続きを読む
栃木県について考えてみたいと思います。
栃木県は、関東地方北部に位置しますが、実際に東は茨城県になり、西には群馬県、南側には茨城県、埼玉県、群馬県の三県。そして北には、福島県と接した内陸県になり、首都である東京からは、北方60km~160kmの位置になるのです。
そして、県の東部には標高300m~1,000mの間になだらかな山々で連なる八溝山地。北部から西部へは、那須連山、帝釈(たいしゃく)山地、日光連山、足尾山地からのなだらかな山岳地帯になり、その中でも特に日光連山は、白根山に男体山、女峰山などの標高2,000mを超える火山が連なるのです。順に北部、中央部~南部にかけて、那珂川、鬼怒川、渡良瀬川流域の平野が広がっています。
栃木県は、県土の約55%は森林が占める自然豊かな県なのです。
その北部から西部へかけた山岳地帯では、日光国立公園にも指定されており、国際観光地日光をはじめとし、全国的にも知られる那須、塩原、鬼怒川、川治と、数多くの観光資源に大変恵まれている地域になります。
県では栃木県グリーン調達推進方針とし、環境への負荷が少なくし持続可能な循環型社会への形成を図り、平成12年5月には循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとした「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法 )」も制定されました。
又、同法に基づいて、環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)を優先的に調達し、率先した取り組みを行うことで、環境物品等が市場の形成や開発をも促進し、持続的な発展が可能な社会の構築を進めてきたのです。
平成13年度から、毎年度にわたる「栃木県グリーン調達推進方針」を定め、グリーン調達を推進してきました。
平成17年4月施行の「栃木県生活環境の保全等に関する条例」第63条では、県が行う環境物品等の調達に関しては、毎年度方針を作成・公表すると定めています。
【平成29年度 栃木県グリーン調達推進方針】
平成29年2月に策定された国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」を参考に、「平成29年度栃木県グリーン調達推進方針」を策定しました。
方針の「平成29年度環境配慮物品等調達目標」では、22分類 274品目についての判断基準に適合した物品等を優先的に調達するとし、その目標を定めているのです。
(公式ページより一部引用)
これを、お子さまの夏休みの自由研究の題材にしても良いかも知れ麻せんね。
因みに、観光地として名高い宇都宮と栃木は、それぞれ宇都宮県と栃木県が合併するとき、県庁所在地を宇都宮にする代わりに、県名は栃木として合意されたと、栃木に住む子なら学校で習うとも言われています。
それでは、この2つの市を比べてみることにします。
【宇都宮市・栃木市の共通問題】
〇商業業務機能:現状
・商業(売上高等)の衰退
・来街者の減少
・空き店舗の増加
・郊外での大型ショッピングセンター立地等
・商業環境の変化
・宮環の開通
・大型店の撤退
・商店の老朽化等
〇経済のサービス化の進展
・企業の支店の撤退・統合
・産業支援サービスの未成熟等
〇商業機能の再編
・「もの」から「総合的サービス提供」への転換
・商店の個性化
・商業機能と交流機能の融合等
〇商業環境の改善
・回遊ゾーンと都市景観の形成
・交通アクセスの確保
・再開発等
〇交通機能
現状:自動車中心の交通
・交通渋滞
・鉄道・バス利用者の減少
・駐車場の不足等
〇JR駅東西交通の不便性
・自動車依存型からの脱却
・公共交通機関(都市新バス、新交通等の整備
・自動車流入抑制、効率的駐車場整備等
・歩行者・自転車ネットワーク形成 等
・幹線道路・交通結節点の整備
〇生活環境機能
・都市的イメージの希薄
・低い緑・水と都心空間の融合性
・ゆったり歩ける空間や魅力ある街並みの欠如
・文化・情報環境が未成熟
・高次な文化施設、情報発信機能が弱い
・高齢社会に対応したハード面の整備等が挙げられています。
〇課題
・歴史的文化と現代的文化が融合した都市軸
・広場空間の形成
・文化、教育等の交流機能の充実
・文化・教育施設等の整備
・バリアフリー等の推進
〇居住機能の現状
・都心部内での人口減少の進行
・都心コミュニティの崩壊
・少子高齢化の進行等
・無秩序な住商混在の進行
・都心コミュニティの再生
・多様な利便施設の立地
・都市型居住地の整備
・良好な居住環境の保全と確保等
・土地利用ルールの確立
・商業業務地区と住宅地区との適切な土地利用ルールの確立等
こうして具体的に掲げると、どれも早く解決したい問題ばかりですね。
ただ、どれだけ設備を整えても、この様な問題への対応はこの土地ながらであり、自然との共生方法が必要でしょう。
栃木県内において、平成29(2017)年度に4件の人身事故が発生しています。
これは記録のある平成10(1998)年度以降最多(平成25年度と同数)の発生件数となっているのです。
・6月12日:佐野市飛駒町地内で、登山者(40代男性)が頭や両腕を咬まれる重傷
・7月15日:那須町高久乙地内で、有害鳥獣捕獲従事者(60代男性)が顔を引っかかれるなどの軽傷
・8月5日:那須町大島地内で、釣りをしていた人(50代男性)が頭や背中を咬まれるなどの軽傷
・9月11日:佐野市飛駒町地内で、きのこ採りをしていた人(70代男性)が顔や腕、腹などを引っかかれるなどの軽傷
クマによる人身事故防ぐためには…
普段はおとなしい動物ですが、時には人が襲われることもあります。
このため、クマによる人身事故を防ぐには、クマと出会わないことが最も大切です。
・クマによる人身事故
・クマによる人身事故を未然に防ぐための注意喚
1.クマがいそうな場所には行かない
2.早朝や夕方は特に注意
3.一人での行動を避ける
4.鈴や笛、ラジオ等を身に付け、音を出しながら歩く
もしもクマに出会った時。
クマが人を襲う理由の多くは、自分の身や子グマを守るためです。
このため、クマを刺激しないことが大切です。
1.静かにゆっくりとクマから離れる
2.クマに背中を向けない、走って逃げない
3.グループで固まる
4.子グマには絶対に近付かない
これらを知り、少しでも考える事が出来ましたでしょうか。
それでは、小山氏の祖とされる小山政光と、その妻でる鎌倉幕府より地頭に任ぜられた寒川尼がモデルとなる、ちょっぴり勝気な寒川尼(さんがわに)ちゃんの二人が、小山市のベストカップルとされてもいる、平成24年4月から、ふるさと「おやま」を全国発信にもあやり、トラブルの無い良い夏をお過ごしください。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
栃木県のデザイン注文住宅ならマレアハウスデザイン
宇都宮市インターパーク・小山市中久喜に総合展示場を
展開中!
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-